スマホ育児、どこまでOK?
目次
乳幼児の脳を育てる「関わり方」とは
こんにちは!0歳からの育脳コーチ・みゆき先生です。
最近は、ちょっとしたスキマ時間や子どもがグズったときに「ついスマホを見せちゃう…」というママやパパも多いですよね。
でも実は、乳幼児期の「スマホ育児」が、子どもの脳の育ちに大きな影響を与えることがわかってきています。
「でもどう関わればいいの?」「スマホ以外にどうしたらいいの?」
そんな疑問に、育脳の視点からわかりやすくお答えします。
赤ちゃん・幼児がスマホに夢中になるのはなぜ?
- スマホは「光」「音」「動き」など、脳を刺激する要素がたっぷり
- 視覚や聴覚の発達が盛んな乳幼児期にとって、スマホは魅力的
- じっと見ているのは、「脳が刺激に反応して育っている証拠」
📌 ポイント
興味を持つこと自体は自然な発達過程です。
「見てる=悪い」ではなく、「なぜ興味を持つのか」を知ることが大切です。
スマホ育児に潜むリスクとは?
一方で、スマホを見せすぎるとこんな心配も…。
- 強すぎる刺激に慣れすぎて、日常の遊びに集中できなくなる
- 受け身の時間が増え、非認知能力(共感力・集中力・想像力など)が育ちにくくなる
- 親子のふれあいが減り、脳の土台となる「愛着」や「信頼感」が育ちにくくなる
📌 補足
「静かにしてくれるから…」と使い続けてしまうと、
子ども自身の“考える力”や“やりとりする力”が育ちづらくなります。
スマホは悪じゃない!育脳的「上手な使い方」
「じゃあスマホはダメなの?」
いいえ、そうではありません。
🌿育脳的な使い方のポイント
- 親の休憩時間として“目的をもって使う”のはOK!
- 「静かにしててほしいとき」よりも「あとで関わる時間を取る」が◎
- 見せっぱなしではなく、「あとで一緒に話す」など関わりに変える工夫を
📌 キーワード:
スマホは「育児を楽にする道具のひとつ」。
でも、脳を育てるのは人との関わりです。
スマホに頼りすぎない!今日からできる関わり方3つ
無理なくできる関わりで、脳に心地よい刺激を届けましょう。
- 顔を見て、声をかける時間を意識的につくる
「今どんな気持ちかな?」とつぶやくだけでもOK! - ふれあい遊びや手遊び歌で、五感を刺激する
スマホのかわりに、手・音・動きをたっぷり使って。 - 受け身でなく“自分で動く遊び”を増やす
絵本のページをめくる、ボールを転がす、おままごと…何でもOK!
まとめ
スマホを見せることが「育児の失敗」ではありません。
大切なのは、「見せ方」と「そのあとの関わり方」。
スマホよりも、ママ・パパの声・笑顔・まなざしが、
子どもの脳にとっていちばんのごちそうです。
「完璧じゃなくていい」
でも、「ちょっと意識する」だけで、子どもの未来はぐんと変わっていきますよ。
📌 スマホに頼らない関わり方のヒントはこちら
📩 育児に役立つちょっとしたヒントを受け取ってみませんか?
LINE公式アカウントに登録すると、今だけ育児に役立つPDFをプレゼント🎁
🔹親子の絆を見える化するシート
🔹イヤイヤ期トリセツbook
🔹子どもの気持ちサイン早見シート
育脳のコツや日々の困りごとへの対応にも役立ちます。

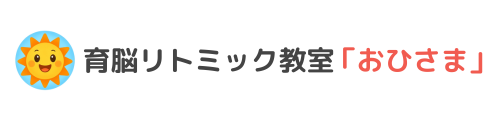


“スマホ育児、どこまでOK?” に対して1件のコメントがあります。