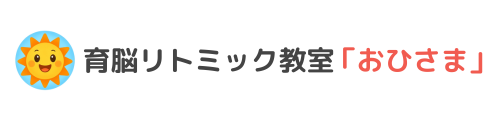子どもが落ち着きがない意外な原因
目次
「うちの子、なんでこんなに落ち着きがないの?」 じっと座っていられない、すぐ立ち上がる、集中が続かない……。
そんな子どもの行動に戸惑い、不安を感じているママは多いのではないでしょうか。
でも実は、それは“性格”や“しつけ”のせいではないかもしれません。
あまり知られていないのですが、「感覚の育ち」が関係している可能性があるのです。
この記事では、子どもが落ち着きがない原因のひとつとして注目される「感覚の発達」について、
そして家庭で簡単にできる遊びを通したサポート方法をご紹介します。
意外と知られていない?感覚には「7感」がある!
私たちがよく知っている「五感」
これらは、子どもの脳の成長に欠かせない大切な感覚です。
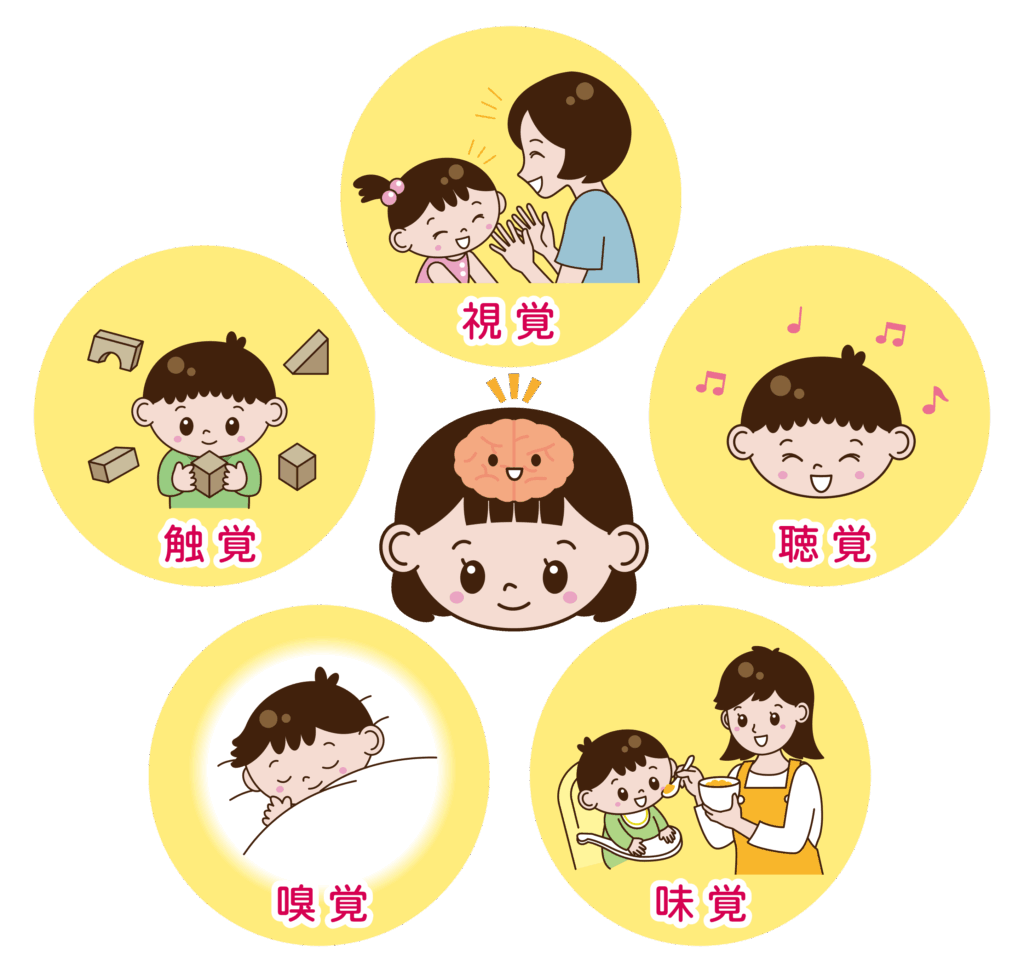
視覚(👀)
人の顔や動きを見ることで、社会性や表情の理解が育ちます。
聴覚(👂)
音楽や話し声を聞くことで、言葉の習得やリズム感が発達します。
触覚(🖐)
ものに触れたり、遊んだりすることで、手先の器用さや安心感が生まれます。
嗅覚(👃)
匂いを通じて、記憶や感情とつながりやすくなります。
味覚(👅)
さまざまな味を体験することで、食育や感覚の刺激にもつながります。
このように五感がバランスよく刺激されることで、子どもの脳はより健やかに育ちます。
しかしながら、それだけでは十分とは言えません。
感覚には、実はもう2つとても重要な感覚があるのです。
子どもが落ち着きがない原因?「前庭覚」と「固有覚」
子どもの成長に大切な感覚は、みんながよく知っている五感だけではありません。
体のバランスや動きを感じる「前庭覚」と「固有覚」という感覚も、とても大切です。
この2つの感覚を合わせて、最近は「7感」と呼ばれることもあります。
つまり、「見る・聞く・触る・嗅ぐ・味わう」の五感に加えて、体の動きやバランスの感覚も大事だということです。
前庭覚とは?〜バランス感覚の土台〜
前庭覚とは、体の傾き・スピード・方向を感じ取る感覚のことです。
この感覚が未発達だと…
- よく転ぶ
- 椅子にじっと座っていられない
- ブランコやすべり台を怖がる
といった行動が見られることがあります。
固有覚とは?〜体の動きと力加減の感覚〜
筋肉や関節からの情報をもとに、体の動きや力加減を調整する感覚です。
しかし、うまく育っていないと…
例えば
- 力が強すぎたり、弱すぎたりする
- 動きがぎこちない
- 感情が不安定になりやすい
という傾向が出ることもあります。
イライラ・落ち着きのなさは「固有感覚不足」かも?
子どもが落ち着かなかったり、すぐにイライラしてしまうとき。
実はそれ、「固有感覚」が不足しているサインかもしれません。
では、どうしたらいいのでしょうか?
まずは、手のひらや腕に“圧”がかかるような遊びを取り入れてみましょう。
こんな遊びがおすすめ
感覚を育てるには、特別なことをする必要はありません。
日常の中でできる、こんなシンプルな遊びが効果的です。
- 粘土遊び
- クレヨンでのお絵描き
- 雑巾しぼり
- タオルやぬいぐるみをギュッとにぎる
こうした遊びは、体に適度な「深い圧」を与えてくれるため、子どもの心と脳が落ち着きやすくなります。
感覚を育てるには「遊び」がいちばん!
日々の中に、感覚刺激を自然に取り入れるには「遊び」が最適です。
そこで以下のような遊びを、意識して取り入れてみましょう。
前庭覚を育てる遊び
- ジャンプ遊び
- くるくる回転する遊び
- ブランコやトランポリン
- 滑り台
固有覚を育てる遊び
- 粘土やスライムでの遊び
- 雑巾しぼり、ハンカチをたたむ
- ギュッと抱きしめる(ハグ)
- 固めの食べ物をよく噛んで食べる
- 砂遊びや泥あそび
その他おすすめの感覚遊び
- ブロック遊び(組み立て、押し込む動作)
- お絵描きや塗り絵
- 洗濯物かごを運ぶなど、少し重い物を持つお手伝い
- センサリープレイ(感覚を刺激するあそび)
まとめ
困った行動の裏にある「感覚の未発達」に注目を
子どもが「落ち着きがない」「注意がそれやすい」「よく転ぶ」などの原因は、
もしかすると感覚の発達が十分でないことが原因かもしれません。
ですが、心配しすぎる必要はありません。
まずは、毎日の遊びの中で、少しずつ感覚を刺激することから始めてみましょう。
楽しみながら、子どもの脳と心の土台を育てることができますよ。
無理なく、日常の中で感覚を育てる遊びを取り入れていきましょう。