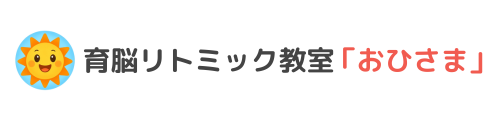有名大学に進む子の3歳までの習慣5選
目次
こんにちは、育脳コーチのみゆき先生です。
今日は、有名大学に進む子の3歳までの習慣についてお話します。
「受験準備は小学校に入ってからで十分」…そう思っていませんか?
実は、0〜3歳は脳がぐんぐん成長する“黄金の時期”。
この時期の遊びや生活習慣は、将来の学力や考える力、人との関わり方まで、大きな土台になります。
たとえば、おしゃべりがまだ拙くても、ママやパパと目を合わせて笑い合った経験。
砂場で山を作って崩した、そんな一見何気ない遊び。
こうした時間が、脳の中にたくさんの“つながり”を作り、後の学びを支える栄養になるのです。
多くの有名大学に進んだ人の幼少期を調べると、0〜3歳の過ごし方に、ある共通点が見えてきます。
今回はその共通点と、家庭でできる温かい関わり方をご紹介します。
1.親子の会話がたっぷりある
小さな子は、大好きな人の声や表情から、言葉の意味や使い方をぐんぐん吸収します。
そのため、日常でたくさん話しかけられた子は、自然と語彙が増え、理解力や読解力の土台が育ちます。
ポイントは、「正しい答えを教える」よりも「一緒に考える」ことです。
💬 会話の一例
- 「これは何色?」ではなく、「この色、何に似てるかな?」
- 「これ何?」ではなく、「これは何に使えると思う?」
こうして会話が広がると、子どもの頭の中で“想像の花”が咲きます。
2.遊びながら学びを体験している
積み木やおままごと、外遊びなど、自由度の高い遊びは創造力や集中力を伸ばします。
0〜3歳の時期は、とくに「会話で説明すること」よりも、身近な人や友だちの動きを真似ることが大切。
真似るうちに想像がふくらみ、言葉もどんどん増えていきます。
🎯 遊びの一例
- 積み木で橋を作ってみる
(バランス感覚+空間認識) - おままごとで「いらっしゃいませ〜」とお店屋さんごっこ
(真似→想像力アップ→語彙習得) - 公園で追いかけっこ
(運動能力+判断力)
3.生活リズムが安定している
睡眠・食事・運動のリズムが整っている子は、脳もスムーズに働きます。
特に睡眠は、日中に得た経験や知識をしっかり脳に刻むために欠かせません。
⏰ 睡眠時間の目安
- 1〜2歳:11〜14時間
- 3歳:10〜13時間
食事では、噛む回数を増やすことで脳への血流が良くなります。
夜9時にはスヤスヤ眠る子の寝顔は、翌日の元気と集中力を作る“最高の準備時間”です。
4.3歳までに家庭でできる具体的アクション
📚 読み聞かせを習慣にする
- 毎日5〜10分でもOK。
- 感情を込めて読むと、物語の理解力と感情表現が育ちます。
- 同じ絵本を繰り返し読むと、安心感と記憶力がアップします。
💬 質問型コミュニケーション
- 「なぜ?」「どうして?」を一緒に考える時間を作る。
- 親の答えは完璧じゃなくても大丈夫。
- 「面白いね!」「じゃあこうだったら?」と話を広げるのがコツ。
🌿 多様な体験を与える
- 自然観察(虫、花、雲など)
- 料理のお手伝い
(混ぜる・盛るなど)
体験が多いほど、脳の中の情報ネットワークが豊かになります。
📱 スクリーンタイムの工夫
- 長時間の動画視聴は受け身になりがち。
- 親子で一緒に短時間見る。
- 見た後に感想を話し合うと、学びに変わります。
5.親子時間をより良くするためのヒント
- 幼児期は“遊び”が一番の学び。
そのため机の勉強は焦らなくて大丈夫です。 - 他の子と比べるより、
「昨日よりできたね!」と
成長を一緒に喜びましょう。 - さらに失敗も大切な経験。
うまくいかない日も笑って過ごせる余裕を持ちましょう。
まとめ
有名大学に進む子は、0〜3歳のうちに
- 親子の会話が多い
- 遊びから学ぶ習慣がある
- 安定した生活リズムを持っている
学力の基礎は、知識の詰め込みではなく、好奇心・考える力・自己肯定感から生まれます。
だからこそ今日からできることを一つずつ取り入れて、お子さんの未来を支える“脳の土台”を一緒に育てていきましょう。